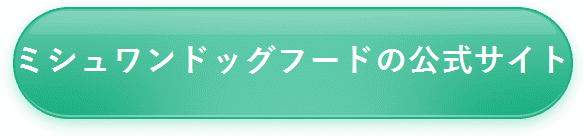ミシュワンの1日の給与量の目安は?体重別に早見表でチェック

愛犬にとって「どれくらい食べればちょうどいいのか」は、健康維持においてとても重要なポイントです。
特に栄養バランスに優れたミシュワンのようなプレミアムフードを与える場合、適切な量を守ることで、その効果を最大限に引き出すことができます。
食べ過ぎは肥満や内臓への負担、少なすぎると栄養不足や元気の低下に繋がるため、正しい給与量を把握することが大切です。
そこで今回は、体重別の給与量早見表をご紹介しながら、1日あたりの目安や回数ごとの分け方など、日々の食事管理に役立つ情報をわかりやすくまとめました。
愛犬の体重に応じてチェックし、健康的な食生活をサポートしていきましょう。
ミシュワンの体重別の1日あたりの給与量について
ミシュワンでは、愛犬の体重に応じて最適な1日の給与量を設けています。
これを目安に食事管理を行うことで、栄養バランスを保ちつつ、肥満や栄養不足のリスクを避けることができます。
下記の表は、体重ごとに必要な1日の給与量と、朝・夜2回に分けた場合の1回あたりの量を示した早見表です。
小型犬から中型犬まで幅広く対応できるため、日々のフード量を見直す際の参考になります。
なお、運動量や年齢、体質によって必要量は多少前後しますので、愛犬の様子を見ながら微調整してあげることも大切です。
特に避妊・去勢後の体重変化や、成長期の子犬には注意して、必要に応じて量を調整しましょう。
| 愛犬の体重 | 1日の給与量の目安 | 1回あたり(2回に分けた場合) |
| 1kg | 約28g | 約14g |
| 2kg | 約47g | 約23.5g |
| 3kg | 約64g | 約32g |
| 4kg | 約79g | 約39.5g |
| 5kg | 約94g | 約47g |
| 6kg | 約108g | 約54g |
| 7kg | 約121g | 約60.5g |
| 8kg | 約134g | 約67g |
| 9kg | 約147g | 約73.5g |
| 10kg | 約159g | 約79.5g |
朝と夜でどう分ける?1日2回が基本だけど、ライフスタイルに合わせてOK
犬の食事回数は、健康維持や消化の負担を考慮して、基本的には1日2回に分けて与えるのが理想とされています。
特にミシュワンのような消化吸収の良いフードであれば、朝と夜に分けて与えることで体への負担も少なく、血糖値の安定や内臓のリズムも整えやすくなります。
ただし、食が細い子や子犬、シニア犬の場合は、3回に分けるなど細かくして与えるのもおすすめです。
また、忙しい飼い主さんで1日2回の食事時間の確保が難しい場合は、自動給餌器を活用したり、朝は手作りごはん、夜はミシュワンという組み合わせもOKです。
愛犬と飼い主さんのライフスタイルに合わせて、無理のない方法で続けることが一番大切です。
ミシュワンは消化が良く、栄養バランスも優れているから、基本は朝晩の2回食が理想
高品質なミシュワンは1日2回に分けて与えることで、消化負担を軽減しながら必要な栄養をしっかり吸収できます。
特に活動量が安定している成犬期には、朝晩の2回食で体調管理がしやすくなります。
食が細い子や子犬、老犬は3回に分けてもOK
一度にたくさん食べるのが難しい子犬や、消化力の落ちてきたシニア犬には、1日3回以上に分ける与え方も効果的です。
無理なく、少しずつ食べさせることで体調も安定しやすくなります。
忙しい飼い主さんは、自動給餌器や朝だけ手作り+夜にミシュワンなどのアレンジもOK
日々の忙しさで決まった時間に与えるのが難しい方は、自動給餌器を活用したり、朝は手作りごはん・夜はミシュワンという“ハーフ手作り食”スタイルもおすすめです。
継続しやすい方法を選びましょう。
実はよくあるNG!体重じゃなく「なんとなく」で量を決めていませんか?
フードの量を「なんとなく」で決めてしまっている飼い主さん、意外と多いのではないでしょうか?「これくらいかな?」とお皿に盛った量が、実は愛犬にとって過剰だったり、逆に足りていなかったりすることは珍しくありません。
体重に対する適正量を基準にしないと、知らず知らずのうちに体調不良や体型の乱れを招くことも。
さらにフードごとにカロリー密度が異なるため、「前のフードで○gだったから今回も同じ量でいいだろう」という感覚で与えるのは危険です。
きちんとした計測には、キッチンスケールや専用の給餌カップを使うのがベスト。
ミシュワンのような高栄養価フードであれば、少量でも十分に必要な栄養が摂れるため、量ではなく“質”を見ることが大切です。
NG・「お皿いっぱいにすればOK」なんて感覚、要注意
見た目だけで「お皿いっぱいに入っていれば安心」と思っていませんか?それはまるで人間がどんぶり飯でカロリーを判断するようなもの。
犬にとって必要なのは、量ではなく中身です。
NG・フードのカロリーは製品ごとに違うから、“前に使っていたフードと同じ量”では危険
フードには製品ごとに異なるエネルギー量が設定されています。
同じg数でも高カロリーになってしまうこともあるため、前のフードと同じ感覚で与えるのはやめましょう。
NG・正確に測るならキッチンスケール or 給餌カップを使ってね
目分量ではなく、数字できちんと管理することが愛犬の健康を守る第一歩です。
毎日のことだからこそ、習慣としてきちんと計測する癖をつけておきましょう。
フードの量だけじゃダメ?おやつ・トッピングの“隠れカロリー”にも注意
フードの量だけをしっかり管理しているのに、愛犬が太ってきた…そんなときに見落とされやすいのが「おやつ」と「トッピング」の存在です。
特に市販のおやつは嗜好性が高く高カロリーなものも多いため、日々の積み重ねがカロリーオーバーにつながります。
また、トッピングでささみや野菜を加えている場合でも、その分フードの量を調整しないと過剰摂取になってしまうこともあります。
愛犬の健康を保つには、1日に与えるすべてのカロリーをトータルで把握しておくことが大切です。
特にミシュワンのように栄養バランスがしっかり取れているプレミアムフードを与えている場合、必要以上のトッピングはかえって逆効果になることもあります。
全体量のバランスを意識しましょう。
おやつは1日の総カロリーの10%以内が理想
ごほうびとして与えるおやつも、油断すると高カロリーになります。
愛犬の健康を守るためには、おやつのカロリーも含めて1日の摂取量を管理しましょう。
目安は1日の総カロリーの10%以内です。
トッピングを多く使うなら、その分ミシュワンの量は減らして調整を
トッピングが多いと、カロリーや栄養バランスが偏る原因にもなります。
ささみやかぼちゃなどを加える場合には、その分フードを少し減らして調整しましょう。
ミシュワンは少量でも栄養満点!だから“量が少ない=足りない”ではない
ミシュワンのようなプレミアムドッグフードは、一般的な市販フードと比べて栄養密度が高く、少量でも必要な栄養素をしっかりと摂取できるよう設計されています。
つまり、見た目の“量”が少なく感じても、それは決して「足りていない」わけではありません。
特にタンパク質や脂肪、ビタミン・ミネラルといった必須成分が高い水準で配合されているため、効率よく体を作り、エネルギー源となります。
これにより、食後の満足感が長く続き、胃腸への負担も少なく済みます。
市販の安価なフードに慣れていると、最初は少なすぎると感じるかもしれませんが、ミシュワンの場合は“量より質”が大切です。
体型や便の状態、食べっぷりを見ながら適正量を見極めていきましょう。
ミシュワンは高たんぱく・高消化性・栄養設計◎のプレミアムフード
しっかりと体を作るために必要な栄養がぎゅっと詰まっているミシュワン。
高たんぱく・高消化性だから、少ない量でも健康をしっかりサポートしてくれます。
市販の安価なフードより吸収率が高いから、実は必要量が少なくて済む
見た目の量だけで判断しがちですが、実際にはミシュワンの方が効率よく栄養が吸収されるため、必要量が少なくて済みます。
体の変化を感じながら調整していきましょう。
給与量はどうやって計算する?ライフステージや運動量で調整しよう【ミシュワン給与量の計算方法】
愛犬にとって理想的な食事量は「犬種」「年齢」「活動量」などにより変わるため、画一的に決めることはできません。
特に小型犬は体が小さい分、摂取カロリーの過不足が体調や体型に直結しやすい傾向があります。
そこで今回は、ミシュワンを与える際に注意したい給与量の計算方法について、年齢(ライフステージ)や日々の活動量別に分けてご紹介します。
単に「体重だけで判断する」ではなく、成長期かシニア期か、室内犬かアクティブ犬かなど、ライフスタイルに応じた柔軟な調整が必要です。
この記事を読めば、愛犬の健康と体型を保ちながら、美味しく・正しくミシュワンを取り入れるヒントがきっと見つかります。
ライフステージ別に違う!年齢や成長段階で必要なカロリーは変わる
犬の年齢に応じて、必要なカロリーや栄養バランスは大きく変わってきます。
子犬期は成長と代謝が活発なため、食事量も多めに必要です。
成犬になると体格が安定し、必要エネルギーも落ち着いてきますが、シニア犬になると今度は代謝が低下し、若い頃と同じ量を与えていると肥満や生活習慣病の原因になることも。
ミシュワンでは年齢による給与量の調整を推奨しており、それぞれのライフステージに応じた目安量が設けられています。
これを参考にしつつ、便の状態や体重変化を観察しながら、微調整していくことが大切です。
年齢に合った給与量を意識するだけで、愛犬の健康維持にぐっと近づけます。
| 年齢 | 特徴 | 給料量調整の目安 |
| 子犬(〜1歳) | 成長が早く、エネルギー消費が多い | 成犬の1.2〜1.5倍を目安に(※小分けが◎) |
| 成犬(1歳〜7歳) | 安定期。
体格も落ち着く |
ミシュワン推奨量が基本ベース |
| シニア犬(7歳〜) | 代謝が落ち、運動量も低下 | 基本量の80〜90%に抑えるのが◎ |
「成犬の量=すべての犬に適量」ではない!
一見、「成犬の給与量をベースにすれば大丈夫」と思いがちですが、実際にはそれがすべての犬にとって適量とは限りません。
例えば、同じ成犬でも食の細い子もいれば、筋肉質でたくさん食べる子もいます。
年齢だけでなく、個々の体質や消化吸収の状態、体調の変化に応じた柔軟な調整が必要です。
特に子犬や高齢犬は代謝や胃腸の働きが成犬とは異なるため、成犬と同じ基準で与えることは危険なこともあります。
食いつきや便の状態、体重増減といった日々の変化に気を配りながら、最適な給与量を“その子に合った量”として考える視点が大切です。
年齢によって吸収・消化能力や活動量が変わるから、ライフステージごとの見直しが大切
年齢を重ねることで代謝は確実に変化していきます。
子犬の頃は吸収力が高く、頻回に食事が必要ですし、シニア期になると消化器官の働きが落ち、食事量も控えめにする必要があります。
その時々の体の状態に合った食事内容と量を見直すことで、長く健康な生活を送るサポートになります。
活動量の違いでも調整を!室内犬とアクティブ犬では必要量が異なる
愛犬の給与量を考えるうえで見逃せないのが「活動量の違い」です。
室内でのんびり過ごす子と、毎日公園を走り回る子では、必要なエネルギー量に大きな差が出ます。
特に小型犬は見た目の体重差が少ないため一律に考えがちですが、実際には消費カロリーに差があるため、フードの量も調整する必要があります。
たとえば、お散歩が1日15分程度の子と、朝夕1時間以上動く子では、1日で消費するカロリーが20%以上違うことも。
ミシュワンでは、この活動レベルに応じた給与量の調整を推奨しており、運動量が少ない子は基本量の90〜95%、逆に活発な子は110〜120%に増やす目安があります。
毎日の運動量をしっかり見極めて、食事量もそれに応じた調整を行いましょう。
| 活動量 | 特徴 | 給与量調整の目安 |
| 低活動(室内犬) | 留守番が多い、散歩短め | 基本量の90〜95%でOK |
| 標準活動 | 毎日30〜60分の散歩あり | ミシュワン推奨量どおりでOK |
| 高活動(外遊び・スポーツ犬) | ランニング・運動大好きタイプ | 基本量の110〜120%で調整 |
「ちょっと太った?」「最近ごはん残すな…」というときは、活動量に見合ってない量になってるサインかも
体重が増えた、食べ残しが増えた、便がゆるくなった…。
そんなときは、今の食事量が実際の活動量に合っていない可能性があります。
食欲がない=食事が合っていないと短絡的に決めつけず、運動量や生活リズムの変化を振り返ることがヒントになります。
食事と活動のバランスがとれてこそ、愛犬の健康も維持しやすくなります。
避妊・去勢後は要注意!太りやすくなるから少し調整を
避妊・去勢手術を終えたあとの愛犬は、体質に大きな変化が生じることがあります。
特に目立つのが「太りやすくなる」という傾向で、ホルモンバランスの変化によって基礎代謝が低下し、運動量も自然と減少していく傾向にあります。
同じフードの量を与えていても、以前と同じようにはエネルギーを消費しにくくなるため、気づいたときには体重が増えていた、というケースが多く見られます。
ミシュワンのように栄養バランスが良く、食いつきの良いフードを使っていると、つい嬉しくてたくさん与えてしまいがちですが、こうした体の変化をふまえてフードの量を微調整することが必要です。
基本的には、避妊・去勢後は定期的な体型チェックとともに、フードの量を5〜10%減らすことを目安にすると、肥満予防に効果的です。
ホルモンバランスの変化で代謝が落ち、脂肪がつきやすくなる
避妊・去勢手術後の犬は、性ホルモンの分泌が止まることで代謝が下がり、カロリーを効率よく消費できなくなります。
これは人間と同じで、食べる量を以前と変えていなくても脂肪がつきやすくなる原因になります。
さらに運動量も減りがちになるため、全体のエネルギーバランスが崩れやすくなり、気づかないうちに太っていたというケースも珍しくありません。
このタイミングでフードの量を見直すことは非常に大切です。
去勢・避妊後の愛犬には、基本量から5〜10%減らすのがおすすめ
太りやすさを防ぐには、フードのカロリーコントロールがカギになります。
避妊・去勢後は、今までのフード量から5〜10%減らすのが一つの目安です。
たとえば1日100g与えていた場合、90〜95gに減らして様子を見てみましょう。
それだけでも徐々に体重の増加が抑えられ、体型をキープしやすくなります。
フードの質が高ければ、栄養不足にはなりません。
| 状況 | 調性目安 |
| 避妊・去勢済み | 給与量を5〜10%減 |
| 去勢+低活動 | さらに抑えて15%減も検討 |
| 痩せすぎの場合 | 維持 or 栄養補助の相談も◎ |
体型チェックで“適正量かどうか”を日々確認しよう
フードの量が愛犬に合っているかを判断するためには、体重の数字だけでなく、体型をこまめにチェックすることが重要です。
そこで役立つのが「ボディコンディションスコア(BCS)」です。
BCSは、肋骨の触れやすさや腰のくびれの有無をもとに、犬の体型を5段階で評価する指標です。
特にBCS3が理想的な体型で、肋骨が軽く触れる程度で、ウエストに自然なくびれがある状態を指します。
太りすぎのBCS4~5では、フードを10〜15%減らす必要がありますし、痩せすぎのBCS2では、栄養補給を検討すべきです。
日々の生活の中で、愛犬の見た目や触り心地を意識しながらチェックすることで、過不足のないフード管理が可能になります。
| スコア | 見た目の特徴 | 給与量の目安調整 |
| BCS 3(理想) | 肋骨は触れるが見えない。
ウエストくびれあり |
現状維持でOK |
| BCS 4〜5(太め) | 肋骨が触れにくい、くびれがない | 給与量を10〜15%減らす |
| BCS 2(痩せ気味) | 肋骨が浮き出て見える | 給与量を10〜20%増やす |
迷ったらどうする?まずは公式量を基準にスタートして様子を見るのが正解
どれだけ情報があっても、「うちの子にはどのくらいが適量なのか?」と迷ってしまうのは当然です。
そんなときは、まずはミシュワン公式サイトに掲載されている体重別の給与量目安に従ってスタートするのが正解です。
スタート後は、2〜3週間ごとに「便の状態」「体重の変化」「食べ残しの有無」などをチェックしながら、必要に応じて5g単位で量を調整するのがおすすめです。
フードは薬ではないので、すぐに体に変化が出るものではありません。
だからこそ、焦らず、じっくりと愛犬の反応を見ながら調整していく姿勢が大切です。
数字だけに頼らず、愛犬の表情や動きからもサインを読み取っていきましょう。
最初は公式サイトが出している給与量(体重ベース)に従う
体重別の給与量はあくまでも“標準的な目安”ではありますが、最初に迷ったらこの数値に従って始めるのが安心です。
最初から過剰に調整しすぎると、かえって不安定になることもあるので、まずは基本に沿ってみて、様子を見ながら微調整していくのがベストです。
2〜3週間ごとに「便の状態」「体重の変化」「食べ残しの有無」をチェック
給与量の見直しタイミングとして、2〜3週間ごとに便や体重、食べ残しなどをチェックするのが効果的です。
便が硬すぎたりゆるすぎたりする場合は、吸収や消化がうまくいっていない可能性があります。
日々の様子を記録するのもおすすめです。
問題があれば、少しずつ+5g/−5gで調整するのがベスト
食べ残しが多い、太り気味、便が不安定などのサインが出たら、フードの量を一気に変えずに5gずつの微調整をしましょう。
急な変化はストレスや体調不良の原因になります。
微調整を繰り返して、ぴったりのバランスを探していくのが愛犬の健康管理の秘訣です。
ミシュワンは子犬に与えてもいい?子犬にミシュワンを与えるときの注意点とポイント
子犬にフードを与えるときは、「いつから?」「どのくらい?」「ふやかすべき?」など、さまざまな疑問がつきものですよね。
成長期の大切な時期だからこそ、安全性や栄養バランスには特に気をつけたいところです。
ミシュワンは全犬種・全年齢対応のプレミアムフードとして設計されており、公式にも子犬から与えられることが明言されています。
ただし、適した時期や与え方を守らないと、消化不良や下痢といったトラブルにつながることもあります。
ここでは、生後何ヶ月から与えてよいかという基本情報から、月齢別のフードの与え方、給与量や回数、注意点までをわかりやすくご紹介します。
子犬の健やかな成長を支えるためのフード選びと与え方を、しっかり学んでいきましょう。
ミシュワンは子犬にも使える?公式の対応と推奨時期について
ミシュワンは「オールステージ対応フード」として、成犬だけでなく、離乳を終えた生後3ヶ月以降の子犬にも安心して与えることができます。
公式見解では、離乳後の子犬から使用可能とされており、AAFCO(米国飼料検査官協会)の基準を満たしていることから、成長期に必要なエネルギーや栄養素もしっかりと網羅されています。
これにより、子犬期から老犬まで、ライフステージに応じてフードを切り替える必要がないという点も魅力です。
とはいえ、月齢が浅い段階ではまだ消化機能が未発達なため、与え方に工夫が必要です。
ミシュワンは栄養面でも安心ですが、成長段階に応じた調整をして与えることが、健康な成長をサポートする鍵になります。
公式見解:生後3ヶ月(離乳完了)以降の子犬から使用OK
公式には、生後3ヶ月の離乳が完了した子犬からミシュワンの使用が可能とされています。
これは子犬の胃腸機能がある程度整ってきて、固形のドライフードをふやかすことで消化できるようになるタイミングです。
急な切り替えを避け、徐々に慣らすことが大切です。
AAFCO基準を満たしている「オールステージ対応」だから、成犬・老犬も同じフードでOK
ミシュワンはAAFCOの栄養基準に準拠しており、子犬からシニア犬まで同じフードでカバーできる設計になっています。
栄養バランスが整っているため、ライフステージごとにフードを切り替える手間がなく、継続的に与えることが可能です。
成長期のエネルギーにも対応できる設計で安心
子犬の成長にはたっぷりのエネルギーと高品質なタンパク質が欠かせません。
ミシュワンは鶏肉を主原料に使用し、良質な動物性タンパクが豊富なうえ、消化にも配慮されています。
これにより、骨や筋肉、内臓の成長をしっかりサポートできます。
子犬への与え方|ふやかす?回数は?段階的な進め方を解説します
子犬にミシュワンを与える際は、月齢に応じてフードの形状や回数を工夫する必要があります。
生後3ヶ月〜4ヶ月の離乳後の子犬は、まだ歯や消化機能が未熟なため、15分ほどお湯でふやかしてから与えるのが基本です。
5〜6ヶ月に入ると、徐々にそのままのフードにも慣れてきますが、最初は半分ふやかして食べやすさを保つのがよいでしょう。
そして、7ヶ月以降になれば成犬食へとスムーズに移行できるようになります。
食事の回数も月齢ごとに見直すことが大切で、成長に合わせて4回→2回へと減らしていくのが一般的です。
無理に早く切り替えようとせず、愛犬の様子を見ながら徐々にステップアップしていくのがポイントです。
| 月齢 | 状態 | フードの与え方 | 回数 |
| 生後〜2ヶ月 | 離乳期 | ✖使用不可(離乳食) | 4〜5回/日 |
| 3〜4ヶ月 | 離乳後 | お湯でふやかす(15分程度) | 3〜4回/日 |
| 5〜6ヶ月 | 成長期 | 半ふやかし or そのまま | 3回/日 |
| 7ヶ月以降 | 成犬食移行 | そのままでOK | 2回/日(朝夕) |
子犬にあげすぎ注意!成犬と同じ給与量にしない
子犬は体が小さいのにエネルギーの消費が激しいため、「たくさん食べさせたほうが元気になる」と思いがちですが、これは大きな間違いです。
子犬の胃腸はまだ未熟で、一度にたくさんの量を消化吸収することができません。
そのため、成犬と同じ量を与えてしまうと、消化不良や下痢、最悪の場合は嘔吐などの体調不良を引き起こす原因になります。
ミシュワンは子犬にも対応できる栄養設計になっていますが、だからといって量まで同じにするのはNG。
基本は少量を回数で分ける方法がベストです。
また、子犬は急激な体重増加も避けるべきなので、定期的に体重をチェックしながら、少しずつ量を調整していくことが大切です。
最初は「ちょっと少ないかな?」と感じるくらいがちょうどよいのです。
子犬は体が小さいわりに消化力が未熟だから、1回の量は控えめが基本
見た目には小さな体でも、内臓もまだ成長途中です。
たとえフードが栄養豊富であっても、一気に多く与えては吸収しきれず負担になることがあります。
1日の給与量は、複数回に分けてこまめに与えるのが理想です。
成犬の給与量をそのまま当てはめると、胃腸トラブルや下痢の原因になる
体格や消化機能が違うのに、成犬の基準で与えてしまうと、過剰摂取になってしまいます。
消化できない分が腸に残り、軟便や下痢の原因になるだけでなく、食欲不振や栄養吸収の妨げにもつながります。
よくあるNGとその対処法|「食べない」「お腹を壊した」時のチェックリスト
愛犬がごはんを食べない、下痢をしてしまった、吐き戻してしまった…そんなトラブルに直面したとき、慌ててしまう飼い主さんも多いと思います。
ですが、こういったトラブルには必ず原因があり、対処法を正しく知っていれば落ち着いて対応できます。
たとえば、食べない原因はフードの香りや粒の大きさが合っていない場合が多く、ふやかしたり細かく砕くことで食いつきが改善されることがあります。
また、急なフード切り替えや食べすぎによって下痢になることも。
こうした時は前のフードと少しずつ混ぜて与えることで胃腸への負担を減らすことができます。
吐き戻しについても、空腹時間が長くなりすぎていたことが原因の場合があるため、1日の食事回数を分けるだけで改善されることも。
困ったときには、以下のチェックリストを活用して冷静に対応していきましょう。
| 問題点 | 原因 | 対策 |
| 食べない | 粒が大きい/香りになれない | ふやかす/すりつぶす/香り付け |
| 下痢・軟便 | 食べすぎ/急な切り替え | 少量から/前のフードと混ぜる |
| 吐いた | 空腹時間が長すぎた | 1日3〜4回に分けて与える |
成長に合わせた切り替えを!子犬→成犬で給与量も変わる
子犬の時期は、体がどんどん成長していく大切な時期。
そのため、1ヶ月前はちょうどよかったフードの量が、今の身体には足りなくなっているということも珍しくありません。
特に生後2ヶ月から7ヶ月くらいまでの間は、1〜2週間ごとに体重や食べ方を見直し、フードの量も調整してあげるのが理想です。
成長が落ち着いてくる7〜9ヶ月頃からは、成犬と同じような給与量に切り替えていっても大丈夫ですが、急に切り替えるのではなく、体格の様子や便の状態を見ながらゆるやかに調整するのがポイントです。
また、定期便を利用している場合は、配送量やサイクルが成長に追いついていないこともあるため、配送ペースの見直しも忘れずに。
ライフステージの変化に合わせた柔軟な対応が、健康な成長をサポートします。
子犬は体が大きくなるたびに必要量も増えるから、1〜2週間ごとに見直しをする
成長期の子犬は、ほんの1〜2週間で体重が大きく変わることもあります。
そんな変化に合わせて、フードの量をこまめに調整していくことで、栄養不足や食べ過ぎを防ぐことができます。
成長曲線に合わせた柔軟な対応が、健やかな発育のカギになります。
7〜9ヶ月頃からは成犬と同じ給与量を目安にOK(体格と便の様子で判断)
生後7ヶ月を過ぎると、体格も落ち着いてきて消化機能も安定しやすくなります。
この頃からは、成犬用の給与量を基準にして問題ありません。
ただし、便がゆるい・硬すぎるなどの変化がある場合は、量を微調整しながら様子を見ることが大切です。
定期便を使ってるなら、1回の配送量や間隔も調整してあげて
子犬の成長にあわせてフードの量が増えると、定期便で届くフードの量や頻度が足りなくなってくることがあります。
逆に、量を減らすべきシニア犬には多すぎることも。
定期購入を利用している場合は、成長段階ごとに配送内容の見直しも忘れずに行いましょう。
【ミシュワンの給与量は合っている?】給与量が合っていないサインとは?よくあるNG例と対策
愛犬の健康を維持するうえで最も重要なのが「毎日の食事」です。
どんなに栄養バランスの良いフードを選んでいても、給与量が合っていなければ本来の効果は発揮できません。
実は、多くの飼い主さんがフードの量を「なんとなく」で与えており、気づかぬうちに愛犬の体調不良や体重の増減につながってしまっていることもあります。
特にミシュワンのような高品質フードを使用している場合は、適正量を守ることで初めて涙やけや毛並み、腸内環境の改善といった本来のメリットを実感できます。
この記事では、給与量が合っていないときに現れるサインや、やってしまいがちなNG例とその対策について詳しく解説していきます。
愛犬の“今”の状態を見直すきっかけにしてみてください。
給与量が合っていないとどうなる?まずは見逃せないサインをチェック
「フードは毎日与えてるし、体重もなんとなくキープしているから大丈夫」と思っていませんか?でも実際には、給与量が合っていないことでじわじわと不調が現れていることも少なくありません。
例えば「食べ残しが多い」「便がゆるい」「食いつきが悪い」などの症状は、ほんの些細な違和感に見えても、実はフード量が原因になっていることがあります。
特に小型犬は体が小さいぶん、少しの量の違いが大きく影響するため、飼い主が見逃さないことが大切です。
下記の表では、よくある症状とそれに関連する可能性のある原因を一覧で紹介しています。
当てはまるものがあれば、今一度給与量や与え方を見直してみると良いかもしれません。
| 症状 | 内容 | 可能性のある原因 |
| 食べ残しが多い | 毎回少しずつ残す | 量が多すぎる/好みに合わない |
| 便がやわらかい・下痢ぎみ | 毎回ゆるい便が出る | 消化不良・一度に多すぎる |
| 便がコロコロ・硬すぎる | 水分不足 or 給与量が少なすぎる | 水分を小まめに与える |
| 体重が急に増えた・減った | 体型チェックが必要 | カロリー過多 or 栄養不足 |
| 食いつきが悪い | いつもダラダラ食べる | フードへの飽き・量の見直しが必要な可能性 |
よくあるNG①:「体重だけ見て量を決めている」
ミシュワンのようなフードを与える際、体重を基準に給与量を調整するのは間違いではありませんが、それだけでは不十分です。
体重が同じでも、年齢や運動量、生活スタイル、さらには体質によって必要なカロリーは大きく異なります。
たとえば、同じ3kgの犬でも、活発に動き回る子と、家でのんびり過ごす子では消費するエネルギー量に差があるため、フードの適量も当然違ってきます。
特に注意したいのは避妊・去勢手術を受けた犬や高齢犬で、ホルモンバランスや代謝の変化により、太りやすくなる傾向があります。
こうした個体差を考慮せず、単純に「体重だけ」で量を決めてしまうと、気づかないうちにカロリー過多や栄養不足につながってしまう可能性も。
体調や体型の変化をこまめに観察しながら、フードの量を柔軟に調整していくことが大切です。
体重が同じでも、年齢・活動量・体質によって必要なカロリーは変わる
見た目や数字が同じ体重でも、中身はまったく異なることが多いです。
若くて元気な子と、シニア期で代謝が落ちている子では、必要な栄養バランスも給与量も違って当然。
日々の様子をよく観察しましょう。
特に避妊・去勢後の犬や高齢犬は代謝が落ちて太りやすくなる傾向がある
ホルモンのバランス変化や筋肉量の減少により、同じ量を食べていても脂肪がつきやすくなってしまうのが避妊・去勢後やシニア犬の特徴です。
この時期は特にカロリー管理に気をつける必要があります。
よくあるNG②:「ごほうび・おやつのカロリーを計算に入れていない」
日々のしつけや癒しとしておやつを与える習慣がある方も多いと思いますが、その“ごほうび”が愛犬の体重増加に繋がっていることもあります。
フードの量を正しく量っていても、実はその横で与えているおやつが1日100kcalを超えていた、というケースは少なくありません。
特に小型犬にとっての100kcalはフード1食分以上のエネルギーに相当することもあり、フード調整が水の泡になってしまう恐れがあります。
ミシュワンのように必要な栄養をしっかり満たすフードを使っている場合は、そもそも追加でおやつを与える必要性が少なくなります。
与える場合でも、1日あたりの総カロリーの10%以内にとどめることが理想です。
食事とおやつ、どちらもトータルで見て管理していきましょう。
フードの量は合っていても、おやつで1日100kcalオーバーなど
おやつは1つ1つが小さいため、つい与えすぎてしまいがちです。
特に複数回にわけて与えることで、気づかぬうちにカロリーオーバーになっていることもあります。
これではどんなに良質なフードを与えていても意味がありません。
カロリーも愛情と一緒に管理しましょう。
ミシュワンのような栄養バランスの取れたフードを使っているなら、おやつは全体の10%以内が基本
毎日のフードで十分に栄養が満たされているなら、おやつは“特別なご褒美”として考えるべきです。
愛犬にとってはおやつ=愛情ですが、その頻度と量には明確な上限を。
与えすぎはかえって健康の妨げになります。
よくあるNG③:「食いつきが悪い=量が少ないと思い込んでいる」
愛犬がフードを残す、食べるスピードが遅くなるといった行動を見ると、「足りないのでは?」と考えて量を増やしてしまう方がいますが、実は逆効果になることもあります。
実際には、すでにお腹いっぱいで食べきれなかったり、胃腸に負担を感じていることが原因で食欲が落ちていることも珍しくありません。
特に子犬やシニア犬のように胃腸がデリケートな時期には、一度にたくさん与えることで消化不良や吐き戻しを起こすリスクが高くなります。
ミシュワンは高栄養価のプレミアムフードであるため、必要な栄養は少量でも摂取可能です。
量を増やす前に、一度フードの質や与え方を見直し、体調や活動量と照らし合わせて調整してみることが重要です。
食べきれないほど量が多すぎて食欲が落ちてるケースも多い
フードの見た目量だけに注目して「足りないかも」と思いがちですが、実はそれが過剰であることも。
毎回食べ残している場合は、まずは与えすぎを疑ってみましょう。
満腹感が原因で食いつきが悪くなることもあります。
特に子犬やシニア犬は、一気に多くを与えると胃腸に負担がかかるだけでなく、偏食や嘔吐につながることもある
消化器官が未発達な子犬や、機能が低下しているシニア犬は、一度に大量のフードを与えることで不調を起こしやすくなります。
小分けで回数を増やしたり、ふやかして与えるなどの工夫が必要です。
ミシュワンの給与量は?についてよくある質問
ミシュワンの給与量の計算方法について教えてください
ミシュワンの給与量は、愛犬の「体重」「年齢」「活動量」によって細かく調整する必要があります。
基本の目安として、公式サイトには体重ごとの推奨グラム数が掲載されており、たとえば3kgの成犬であれば1日あたり約60g程度が推奨されています。
ただし、これはあくまで標準活動レベルの成犬に対する数値であり、子犬やシニア犬、あるいは室内飼育で活動量が少ない犬にはさらに調整が必要です。
活動量が低い場合は基本量の90%程度に抑え、逆に運動量が多い犬は110〜120%を目安に調整するのが一般的です。
また、避妊・去勢後は代謝が落ちやすいため、さらに5〜10%ほど減量するのが理想です。
フードの量は、便の状態や体重変動を見ながら、2〜3週間単位で微調整することが大切です。
関連ページ:ミシュワンの給与量は?計算方法や与え方・子犬に与えるときの注意点
ミシュワンをふやかして与える方法について教えてください
ミシュワンをふやかして与える方法は、子犬やシニア犬、あるいは胃腸が敏感な犬にとって非常に有効な食べさせ方のひとつです。
やり方はとても簡単で、ドライフードを器に入れたら、ぬるま湯(約40℃前後)をフードがひたる程度注ぎ、5〜10分ほど待つだけ。
ふやけたミシュワンは香りが立ちやすくなるため、食いつきが悪い子にもおすすめです。
注意点としては、熱湯を使うと栄養成分が損なわれたり、フードの風味が変わってしまうことがあるため避けましょう。
また、ふやかしたフードは雑菌が繁殖しやすいので、常温で長時間放置せず、必ず1回で食べきれる量を用意するようにしてください。
体調が安定してきたら、少しずつドライに戻していくとスムーズです。
関連ページ:「ミシュワン ふやかし方」へ内部リンク
ミシュワンを子犬に与える方法について教えてください
子犬にミシュワンを与える際は、「消化力」と「噛む力」の発達段階に注意しながら、少しずつ慣らしていくのがポイントです。
生後2ヵ月以降であればミシュワンを与えることができますが、最初はふやかして柔らかくしてから与えるのがおすすめです。
回数は1日3~4回の小分けが理想で、胃腸に負担をかけないように少量ずつ与えていきましょう。
また、成長期は体重や体格の変化が著しいため、2週間おきに体重を測定し、必要に応じて給与量を調整することが大切です。
便の状態や食いつきをよく観察し、下痢や嘔吐がある場合は、フードの量や与え方を見直す必要があります。
しっかり食べて、しっかり育つ。
そのためには“合った量”と“正しい方法”がカギになります。
関連ページ:「ミシュワン 子犬 与え方」へ内部リンク
愛犬がミシュワンを食べえないときの対処法について教えてください
愛犬がミシュワンを食べないときは、まず“食べない理由”を冷静に見極めることが重要です。
フードの味に飽きたというよりも、体調や環境の変化、ストレスによる一時的な食欲低下が原因の場合もあります。
まずは常温に戻したり、ぬるま湯でふやかして香りを引き出すなどの工夫を試してみましょう。
それでも食べない場合は、トッピングとして少量の鶏ささみやゆで野菜を混ぜることで、食欲を刺激できます。
ただし、トッピングの割合はフード全体の10%以内にとどめ、栄養バランスが崩れないよう注意が必要です。
しばらく様子を見ても改善しない場合は、体調不良のサインかもしれないため、かかりつけの獣医師に相談することをおすすめします。
関連ページ:「ミシュワン 食べないとき」へ内部リンク
ミシュワンドッグフードは他のフードとはどのような点が違いますか?
ミシュワンドッグフードが他のフードと大きく異なる点は、「ヒューマングレード品質」「無添加」「グルテンフリー」「獣医師監修」という4つの軸を徹底していることです。
使用されている原材料は、すべて人が食べても問題のないレベルのものを選定しており、保存料や着色料、香料といった人工添加物を一切使用していません。
また、アレルギーリスクを抑えるためにグルテンを含まない設計となっており、体の内側から健康を整えることを重視しています。
さらに、栄養バランスは獣医師が監修しており、被毛・関節・胃腸など、現代の小型犬が抱えがちな悩みに寄り添った成分配合が魅力です。
市販フードと比べて安心感と機能性を兼ね備えた総合栄養食です。
ミシュワンは子犬やシニア犬に与えても大丈夫ですか?
ミシュワンは全年齢・全犬種対応の総合栄養食として設計されており、生後2ヶ月以上の子犬から、7歳以上のシニア犬まで安心して与えることができます。
特に子犬期には骨格や筋肉が急速に発達するため、タンパク質や脂質、ビタミン・ミネラルのバランスがとても大切です。
ミシュワンにはヒューマングレードの国産鶏肉を中心に、アマニ油やビフィズス菌など、発育と腸内環境を支える成分が含まれています。
一方、シニア期の愛犬には、消化しやすく内臓に負担をかけない食材が重要です。
ミシュワンは添加物不使用で、低アレルゲン設計かつグルテンフリー。
シニア犬でも食べやすく、毎日の栄養補給に適しています。
年齢に合わせた給与量の調整とともに、長期的に健康を支える食事としておすすめです。
ミシュワンは犬種・体重によって給与量を変えますか?
はい、ミシュワンの給与量は犬種よりも体重と活動量に応じて調整するのが基本です。
公式サイトには体重別の給与量目安が掲載されており、たとえば3kgの成犬であれば1日60g程度が基準とされています。
しかし実際には、活動量の多さや代謝の違いによって必要なカロリーが変わってくるため、最初は目安量を参考に与え、便の状態や体重の変化を見ながら5g単位で微調整していくことが推奨されます。
さらに小型犬は消化器官が繊細なため、一度にたくさん与えるよりも、1日2〜3回に分けて与えることで負担を軽減できます。
犬種による差異よりも、個々の体質やライフスタイルに応じた柔軟な対応が求められます。
他のフードからミシュワンにフードを変更するときの切り替え方法について教えてください
ミシュワンに切り替える際は、急な変更を避けて、7日間を目安に段階的に行うのが基本です。
まずは現在のフードに対して10%程度のミシュワンを混ぜるところから始め、2〜3日ごとにミシュワンの割合を10%ずつ増やしていきます。
7日〜10日ほどで完全に切り替えるのが理想です。
犬によっては、急な味の変化や原材料の違いに体が驚いて、下痢や嘔吐などを起こすことがありますが、それは新しいフードに体が慣れていないだけの場合がほとんどです。
もし体調に変化が見られた場合は、無理せず元の量に戻し、少し時間をかけて調整するのが安心です。
切り替え時は、白湯でふやかす・トッピングを加えるなどの工夫も有効です。
好き嫌いが多いのですが、ミシュワンをちゃんと食べてくれるのか心配です
好き嫌いが多いワンちゃんには、初めてのフードへの警戒心が強い場合があります。
とはいえ、ミシュワンは素材の自然な香りと食感を大切にした設計で、多くの犬に高い食いつきが報告されています。
ヒューマングレードの鶏肉を使用し、添加物や香料を使わずに仕上げているため、人工的な強い香りが苦手な子にも合いやすい点が特長です。
初めはフードに対して戸惑いを見せるかもしれませんが、その場合は一時的にふやかして香りを引き出したり、少量のトッピング(茹でたささみやかぼちゃなど)で慣れさせていくと、徐々に自ら口にするようになることが多いです。
無理に切り替えず、愛犬のペースに合わせるのが成功のコツです。
ミシュワンを食べてくれないときの対処法はありますか?
ミシュワンを食べない場合、原因としては「初めての味への警戒」「体調不良」「量が多すぎる」などが考えられます。
まず最初に確認したいのは、食事の環境。
時間を決めて与えているか、フードはいつも新鮮かなど、基本的な点も見直しましょう。
初日は警戒して食べない子もいますが、焦らず、ふやかして香りを立たせたり、トッピングを少し加えることで食いつきが改善することがあります。
また、一度に与える量が多すぎると食欲が落ちることもあるので、推奨量の80〜90%からスタートし、徐々に増やす方法も効果的です。
食べない=嫌いとは限らず、環境や体の状態の影響もあるため、無理に切り替えを急がず、愛犬のペースに合わせた対応を心がけましょう。
ミシュワンに変更したらお腹を壊してしまいました。対処法について教えてください
フードをミシュワンに切り替えた直後にお腹を壊してしまった場合、多くは「切り替えのスピードが早すぎた」「体が新しい成分に慣れていない」といった理由による一過性の反応です。
このような場合は、すぐに以前のフードに戻すのではなく、ミシュワンの割合を一度減らして、ゆっくり時間をかけて再調整するのが理想的です。
また、一時的に白湯でふやかして胃腸の負担を減らす方法も有効です。
便が緩くなっただけであれば、数日で落ち着くケースも多いですが、血便や嘔吐が続く場合には早めに獣医師へ相談を。
特に腸内環境が不安定な子犬やシニア犬は、変化に敏感なため、給与量やタイミングも含めて丁寧に調整していくことが大切です。
ミシュワンの保存方法や賞味期限について教えてください
ミシュワンは無添加・保存料不使用のプレミアムドッグフードであるため、保存方法には特に注意が必要です。
未開封の状態であれば、製造日から約1年間の賞味期限がありますが、開封後は空気や湿気、光の影響で品質が劣化しやすくなるため、1ヶ月以内に食べきるのが理想です。
保存の際は、袋をしっかり密閉するか、密閉容器に移して、直射日光の当たらない冷暗所に保管してください。
特に梅雨時期や夏場は湿気によるカビのリスクがあるため、冷蔵庫よりも湿度管理のしやすい常温の暗所が適しています。
また、開封後に匂いが変わったり、色や手触りに違和感がある場合は、劣化のサインです。
鮮度を保つためにも、清潔なスプーンを使い、清潔に保つことが重要です。
参照: よくある質問 (ミシュワン公式サイト)
ミシュワン小型犬用ドッグフードを比較/給与量はどのくらい?
| 商品名 | 料金 | グルテンフリー | 主成分 | ヒューマングレード | 添加物 |
| ミシュワン | 約2,000円 | 〇 | チキン、野菜 | ✖ | 〇 |
| モグワン | 約2,200円 | 〇 | チキン、サーモン | 〇 | 〇 |
| ファインペッツ | 約1,800円 | ✖ | ラム肉、チキン | 〇 | 〇 |
| カナガン | 約2,300円 | 〇 | チキン、さつまいも | 〇 | 〇 |
| オリジン | 約2,500円 | 〇 | 鶏肉、七面鳥 | 〇 | 〇 |
| このこのごはん | 約2,800円 | ✖ | 鶏肉、玄米 | ✖ | 〇 |
| ネルソンズ | 約2,000円 | 〇 | チキン、野菜 | 〇 | 〇 |
| シュプレモ | 約1,500円 | ✖ | 鶏肉、玄米 | ✖ | 〇 |
| うまか | 約2,600円 | ✖ | 九州産鶏肉、野菜 | ✖ | 〇 |
※アフィリ提携済みの商品は上記の商品名にアフィリリンクを貼る
ミシュワンの給与量は?計算方法や与え方・子犬に与えるときの注意点まとめ
本記事では、ミシュワンの給与量について計算方法や与え方、子犬に与える際の注意点についてまとめてきました。
ミシュワンの適切な給与量は、犬の体重や年齢、活動量などによって異なります。
計算方法を把握し、適切な量を与えることが大切です。
また、子犬に与える際には、成犬とは異なる栄養ニーズや与え方に注意が必要です。
子犬の健やかな成長のためにも、適切な量と与え方を守ることが重要です。
犬の健康と幸福を考える上で、適切な給与量と与え方は非常に重要です。
間違った量や与え方は犬の健康に影響を及ぼす可能性があります。
そのため、計算方法や注意点をしっかり把握し、丁寧に給与することが求められます。
また、定期的な健康チェックや獣医師のアドバイスも大切です。
愛犬の健康を守るために、適切な給与量と与え方を実践しましょう。
ミシュワンの給与量に関する計算方法や与え方、子犬に与える際の注意点を理解し、愛犬の健康管理に役立てていただければ幸いです。
愛情を込めて、健康的で幸せな犬生を送るために、適切な給与量と与え方を心掛けていきましょう。
関連ページ:ミシュワン小型犬用の口コミ/成分や安全性は?メリット・デメリットを解説