すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について
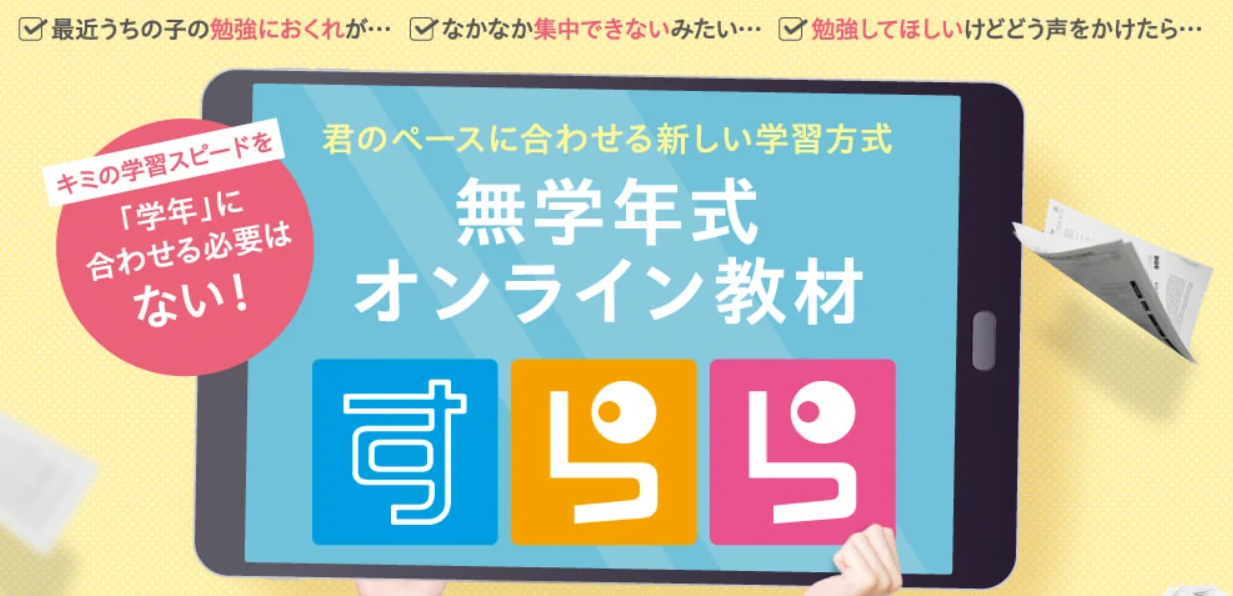
学校に通えない子供にとって、「出席扱い」になるかどうかは非常に重要なポイントです。
文部科学省の方針では、一定の条件を満たしたオンライン学習が「出席扱い」として認められる場合があります。
その中でも、すららは不登校の子供の学習を支援しながら、出席扱いとして認められるケースが増えています。
その理由として、すららの学習システムはしっかりとした学習記録の管理、個別最適化された学習計画、継続的なサポートなどが挙げられます。
学校側が出席扱いとして認めるために重要な要素を満たしているため、すららを活用することで、学習の遅れを防ぎつつ、安心して自宅学習を進めることができるのです。
理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている
すららは、単なるオンライン学習教材ではなく、学習履歴をしっかりと記録できるシステムが整っています。
出席扱いとして認められるためには、学校側に「継続的に学習している証拠」を提示する必要がありますが、すららでは学習内容や進捗状況が自動的に記録され、可視化されるため、この点で非常に有利です。
これにより、学校側も「学習が適切に行われている」と判断しやすくなります。
さらに、学習記録を活用することで、保護者の負担も軽減されます。
学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる
すららでは、学習時間や進捗を自動的に記録し、それをレポートとして出力する機能があります。
これを活用することで、学校側に「どの科目をどれだけ学習したか」「どの単元まで進んでいるか」といった具体的なデータを提示することが可能です。
不登校の子供にとって、単に「勉強している」と伝えるだけでは出席扱いにならないことが多いですが、すららのレポートを活用すれば、学校側に客観的な証拠を提出することができ、出席扱いとして認められる可能性が高まります。
保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい
不登校の子供が家庭学習を進める場合、保護者が学習の記録を手作業で管理し、学校に報告する必要があるケースも少なくありません。
しかし、すららでは、学習の進捗が自動的に記録されるため、保護者が細かく管理しなくても、学校に提出できる学習履歴が簡単に作成できます。
これにより、保護者の負担が軽減されるだけでなく、学校側にとっても「学習状況が明確に把握できる」という点が評価されやすく、出席扱いの判断がスムーズになりやすいです。
理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある
すららは、単なるオンライン学習教材ではなく、専任のコーチがついて学習計画を立てたり、継続的にサポートしたりする仕組みが整っています。
学校側が出席扱いを認める際に重視するのは、「子供が計画的に学習を進めているかどうか」という点ですが、すららではコーチが学習の進捗を管理し、必要に応じてフォローアップを行うため、学習の継続性がしっかり確保されています。
これにより、学校側にも「学習が途切れず、計画的に行われている」ことをアピールしやすくなります。
すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる
すららでは、専任の「すららコーチ」が子供の学習をサポートします。
学校側が出席扱いを認めるためには、「計画的に学習が行われ、継続的に学習している」という証拠が必要になりますが、すららのコーチが学習計画を立て、進捗を管理してくれることで、その点を強くアピールできます。
さらに、コーチのサポートを受けながら学習することで、子供自身も「どこをどのように勉強すればいいのか」が明確になり、学習のモチベーションを維持しやすくなります。
すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる
すららコーチは、子供の学習ペースや理解度を考慮しながら、一人ひとりに最適な学習計画を作成してくれます。
「何をどのくらいのペースで進めればいいのか」が明確になるため、計画性をもって学習を進めることが可能です。
特に、不登校の子供は学校の授業とは異なるペースで学習を進める必要がありますが、すららのコーチが適切なペースを提案しながらフォローしてくれるため、無理なく継続することができます。
すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる
すららの大きな特徴のひとつに「無学年式」の学習システムがあります。
これにより、「ある教科は学年相当のレベルで進めるけれど、別の教科は前の学年の復習から始めたい」といった個別の学習スタイルに対応することが可能です。
不登校の子供の中には、学習の遅れを心配するケースも多いですが、すららなら必要な部分を重点的に学習し、無理なく自分のペースで学習を進めることができます。
学校側にとっても、「学年に関係なく適切な学習ができている」と判断しやすくなるため、出席扱いとして認められやすくなります。
理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる
すららが出席扱いとして認められやすい理由の一つに、家庭・学校・すららの三者でしっかりと連携が取れる仕組みがあることが挙げられます。
不登校の子供が出席扱いとなるためには、学校側に対して「継続的な学習が行われている」という証明を提出する必要がありますが、すららではそのためのサポートが充実しています。
家庭だけで対応するのではなく、すららの専任コーチが間に入り、学習記録の管理や学校との連携をサポートしてくれるため、スムーズに進めることができます。
すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる
出席扱いを認めてもらうためには、学校に対して学習の記録を提出する必要がありますが、どのような書類が必要なのか分からないという保護者の方も多いです。
すららでは、必要な書類の準備方法を案内してくれるため、保護者が手探りで対応する負担を軽減できます。
学校側の要件に応じた学習報告書の作成方法や、提出のタイミングなどについてもアドバイスがもらえるため、安心して手続きを進めることができます。
すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる
すららでは、学習の進捗を可視化するための学習レポートが作成できます。
専任コーチがフォーマットを用意し、どのように記入すればよいのかをサポートしてくれるため、保護者や子供が一人で対応する必要がありません。
学習時間や進捗状況が詳細に記録されたレポートを提出することで、学校側に対して「計画的に学習が進められている」という客観的な証拠を示すことができます。
すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる
不登校の子供にとって、学校との関係が途切れてしまうと、学習の継続が難しくなることがあります。
しかし、すららでは、担任の先生や校長とスムーズに連絡を取るためのサポートも行っています。
学習の進捗状況を学校に報告する際に、どのように説明すればよいかのアドバイスを受けたり、必要な書類を整える手助けをしてもらえるため、学校との連携が取りやすくなります。
理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
すららは、全国の教育委員会や学校と連携し、不登校の子供たちの学習支援を行ってきた実績があります。
そのため、多くの自治体や学校で「出席扱いとなる教材」として活用されており、学校側にとっても認知度が高いことが特徴です。
文部科学省が示す「ICTを活用した学習活動の出席扱い要件」に対応しているため、学校側も受け入れやすいというメリットがあります。
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
すららは、全国の教育委員会や学校と連携し、不登校の子供たちの学習を支援する取り組みを行っています。
そのため、自治体や学校側も、すららを活用した学習がどのようなものかを理解しているケースが多く、出席扱いとして認められる可能性が高くなります。
また、すららの導入実績がある自治体では、学校側の対応もスムーズになりやすいです。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
すららは、文部科学省が示す「ICTを活用した学習活動の出席扱い要件」に対応しており、多くの自治体や学校で不登校支援教材として活用されています。
そのため、学校側にとっても「すららを使って学習しているなら、出席扱いとして認めても問題ない」と判断しやすくなっています。
すでに多くの実績があることで、安心して活用できる環境が整っています。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
出席扱いとして認められるためには、「学習環境が学校に準じたものであること」が重要なポイントになります。
すららは、学校の学習指導要領に沿ったカリキュラムを提供しているため、学習の質が担保されています。
また、学習の進捗状況を記録し、適切なフィードバックを受けることができるため、学校と同じような環境で学ぶことが可能です。
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
すららの教材は、学校の学習指導要領に基づいて作成されているため、学校で学ぶ内容と同じ範囲をカバーすることができます。
これにより、学校側に対して「すららで学習を続けていれば、通常の授業と同等の学習ができている」と説明しやすくなり、出席扱いとして認められやすくなります。
また、子供自身も、学校に復帰した際に授業についていきやすくなるというメリットがあります。
すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある
すららでは、学習の進捗状況が自動的に記録され、テストや確認問題を通じて、理解度を評価するシステムが整っています。
これにより、学習の成果を可視化することができ、学校側に対して「適切な学習が行われている」ことを証明しやすくなります。
さらに、専任コーチが定期的に学習状況をチェックし、必要に応じて学習プランを調整してくれるため、継続的なサポートを受けながら学習を進めることができます。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について
学校に通えない子供にとって、「出席扱い」の制度を利用できるかどうかは重要なポイントです。
文部科学省の方針により、オンライン学習を活用している場合でも、学校の判断によって出席扱いとして認められることがあります。
ただし、申請の手続きにはいくつかのステップがあり、事前に必要な書類や条件を確認しておくことが大切です。
すららを活用して出席扱いを申請する場合、どのように進めればよいのか、具体的な方法について詳しく説明します。
申請方法1・担任・学校に相談する
出席扱いの申請を行う際には、まず担任の先生や学校の担当者に相談することが第一歩となります。
学校ごとに対応が異なるため、どのような条件で出席扱いが認められるのか、また、申請に必要な書類は何かを確認することが重要です。
早めに相談をしておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する
出席扱いとして認められるためには、学校が定める条件を満たす必要があります。
基本的には、以下のような点が重視されます。
– すららのようなICT教材を活用し、継続的に学習を進めていること
– 学習の記録や進捗を学校に報告できること
– 学習内容が学校のカリキュラムに準じていること
学校によっては、追加で必要な書類や申請の流れが異なることもあります。
そのため、担任や学校の担当者とよく相談し、求められる書類を事前に準備しておくと安心です。
申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する
出席扱いの申請において、必ずしも医師の診断書が必要になるわけではありませんが、不登校の理由によっては求められるケースもあります。
特に、体調面や精神的な理由で学校に通うことが難しい場合、医師の意見書が申請をスムーズに進めるための重要な証拠となることがあります。
不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある
学校が出席扱いを認める際に、不登校の理由が重要視されることがあります。
たとえば、
– 適応障害やうつ病などの診断を受けている場合
– 発達障害や感覚過敏など、学校環境が合わないと判断される場合
– 身体的な病気やケガにより通学が困難な場合
これらのケースでは、医師の診断書や意見書を提出することで、「通学が難しいが、家庭での学習は継続可能である」ことを証明しやすくなります。
精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう
医師の診断書が必要な場合、精神科・心療内科・小児科などで診察を受け、現在の不登校の状態や、学習を継続することの重要性について意見書を作成してもらうことができます。
診断書には、「学校に通うことが困難である理由」や「家庭での学習が望ましいこと」などを明記してもらうと、出席扱いの申請がスムーズに進むことがあります。
医師に相談する際は、学校側が求めている情報を事前に伝えておくと、適切な内容の診断書を作成してもらいやすくなります。
申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する
出席扱いの申請を進めるうえで、学校に対して「家庭で適切な学習を継続していること」を証明することが重要です。
すららでは、学習進捗を自動的に記録し、それをレポートとしてダウンロードできる機能があります。
この学習記録を学校に提出することで、客観的な学習証明として活用することができます。
学校側が「この子は適切に学習を続けている」と判断できる材料を揃えることで、出席扱いとして認められる可能性が高まります。
学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出
すららには、学習履歴や進捗状況を自動的に記録し、レポートとして出力できる機能があります。
このレポートには、学習時間、学習した単元、理解度などが記載されており、どの程度学習が進んでいるのかを客観的に示すことができます。
学校側にとっても、「しっかりと学習を続けている」という証拠があることで、出席扱いとして判断しやすくなります。
提出の際は、担任の先生や校長先生と事前に相談し、どのような形でレポートを提出するのがよいか確認しておくとスムーズです。
出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)
出席扱いを申請するためには、学校側で正式な「出席扱い申請書」を作成する必要があります。
この申請書のフォーマットは学校によって異なりますが、一般的に以下のような情報が含まれることが多いです。
・子供の氏名、学年、クラス
・不登校の理由(医師の診断書が必要な場合は添付)
・家庭での学習環境(すららを活用していることを明記)
・学習の進捗(すららのレポートを基に記載)
・今後の学習計画(すららコーチのサポートを活用した継続学習の方針)
学校側が作成する申請書ですが、保護者としても必要な情報を提供し、申請がスムーズに進むようにサポートすることが求められます。
事前に学校と連携し、必要な書類を揃えておくと、手続きが円滑に進みやすくなります。
申請方法4・学校・教育委員会の承認
出席扱いの最終的な判断は、学校長(校長先生)が行います。
文部科学省のガイドラインでは、「校長が適切と判断すれば、オンライン学習を出席扱いとすることができる」とされています。
ただし、自治体や学校によっては、教育委員会の承認が必要なケースもあるため、学校側と連携を取りながら、適切な手続きを進めることが大切です。
学校長の承認で「出席扱い」が決まる
出席扱いの判断は、基本的に校長先生が行います。
文部科学省の方針では、「校長が適切と判断すれば、オンライン学習を出席扱いとすることができる」と定められています。
そのため、学習記録の提出や申請書の作成を通じて、学校側が納得できる材料を揃えることが重要です。
担任の先生と密に連携を取り、校長先生に「家庭での学習が適切に行われている」ということをしっかりと伝えることで、出席扱いとして認められる可能性が高まります。
教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う
自治体によっては、出席扱いの判断を学校だけで行うのではなく、教育委員会の承認が必要な場合があります。
その場合、学校側が教育委員会に申請を行うことになります。
教育委員会への申請が必要な場合、学校との連携がより重要になります。
すららの学習記録や学習計画を整理し、学校側と共有しながら進めることで、スムーズに手続きを完了させることができます。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します
不登校の子供にとって、学校の出席日数がカウントされるかどうかは、将来の進学や学習の継続に大きく影響します。
文部科学省の方針により、オンライン学習を活用することで出席扱いになる可能性があり、その中でも「すらら」は、出席日数を確保しながら学びを継続できる教材として注目されています。
出席扱いを認めてもらうことで、内申点への影響を抑えることができるだけでなく、学習の遅れに対する不安を軽減し、保護者の負担も減らすことができます。
ここでは、すららを活用して出席扱いを得ることの具体的なメリットについて紹介します。
メリット1・内申点が下がりにくくなる
内申点は進学時に重要な指標の一つとなるため、不登校が続いて出席日数が不足すると、評価が下がってしまう可能性があります。
しかし、すららを活用して出席扱いとして認めてもらうことで、出席日数が確保され、内申点の低下を防ぐことができます。
特に、公立高校の受験では、出席状況が評価に大きく影響するため、出席扱いとして認められることは大きなメリットとなります。
出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい
内申点は、学力だけでなく出席状況や授業態度なども評価対象となります。
不登校の状態が続くと、欠席日数が増え、学習状況が良くても内申点が下がってしまうことがあります。
しかし、すららを利用し、学校側が出席扱いとして認めれば、出席日数をカウントできるため、評価が悪化しにくくなります。
また、学習進捗が学校側に共有できるため、「学んでいること」が明確になり、成績にも反映されやすくなります。
中学・高校進学の選択肢が広がる
出席日数が確保されることで、進学の選択肢も広がります。
特に、公立高校の入試では、内申点が一定の割合で考慮されるため、出席日数が多いほど有利になります。
また、私立高校でも、出席状況を重視する学校が多いため、すららを活用して学習を継続し、出席扱いを得ることで、受験の際に有利になる可能性があります。
出席日数が確保されることで、不登校の影響を最小限に抑えながら、自分に合った進路を選ぶことができます。
メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る
不登校が続くと、「授業に遅れてしまうのではないか」「もう取り戻せないのではないか」といった不安を感じることが多くなります。
しかし、すららを活用すれば、自分のペースで学習を進めることができるため、こうした不安を軽減することができます。
学校の授業と同じ範囲を学習できるだけでなく、過去の単元に戻って復習することも可能なため、無理なく学習を継続することができます。
すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい
すららは、無学年式の学習システムを採用しているため、学年に関係なく自分の理解度に応じた学習を進めることができます。
たとえば、国語や数学の基礎を復習しながら、得意な科目は先取り学習をすることも可能です。
これにより、学校の授業と同じペースで進めることが難しくても、必要な知識を身につけながら学び続けることができます。
学校復帰を考えている場合でも、事前に学習を進めておくことで、スムーズに授業に戻ることができます。
学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい
不登校の子供は、「自分は勉強ができない」「周りに遅れている」といった気持ちから、自己肯定感が低下しやすくなります。
しかし、すららを利用して学習を続けることで、「自分も勉強を頑張っている」という実感を持つことができ、自己肯定感の低下を防ぐことにつながります。
また、学習の進捗が記録され、達成感を感じやすい仕組みが整っているため、学習に対する前向きな気持ちを育むことができます。
メリット3・親の心の負担が減る
不登校の子供を持つ保護者は、「学校に行けないこと」「学習の遅れ」「進学への影響」など、多くの不安を抱えがちです。
しかし、すららを活用することで、家庭での学習環境を整えながら、学校との連携もスムーズに進めることができるため、保護者の負担も軽減されます。
特に、学習の進捗をすららコーチが管理してくれるため、親がすべての学習管理をする必要がなくなるのも大きなメリットです。
学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない
すららを利用することで、学校・家庭・すららコーチの三者が連携し、子供の学習を支える体制を作ることができます。
学校側と連携して出席扱いを申請しながら、すららコーチが学習計画をサポートするため、保護者がすべての責任を負う必要がありません。
また、学習の進捗が明確に記録されるため、「子供がどれだけ勉強しているのか」が把握しやすくなり、不安を軽減することができます。
親が1人で悩みを抱え込まずに済む環境が整うことで、家庭全体の負担が減り、子供も安心して学習を続けることができます。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します
すららを活用することで、不登校の子供でも出席扱いとして認められる可能性がありますが、そのためにはいくつかの注意点を押さえておく必要があります。
文部科学省のガイドラインでは、一定の条件を満たしたオンライン学習が出席扱いになるとされていますが、最終的な判断は学校や教育委員会に委ねられています。
そのため、学校側の理解を得ることや、必要な書類を準備することが重要です。
また、不登校の原因によっては、医師の診断書や意見書が求められる場合もあるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。
ここでは、出席扱いを認めてもらうために注意すべきポイントについて詳しく解説します。
注意点1・学校側の理解と協力が必須
出席扱いを認めてもらうためには、学校側の理解を得ることが欠かせません。
文部科学省のガイドラインに沿ったオンライン学習であっても、最終的に出席扱いを判断するのは学校長の裁量となるため、学校側としっかり話し合いを進めることが重要です。
特に、不登校の対応に慣れていない学校では、「オンライン学習で出席扱いにできるのか?」と疑問を持たれることもあるため、具体的な説明が求められることがあります。
まずは担任の先生に相談し、その後、教頭先生や校長先生にも話を通しておくとスムーズに進めやすくなります。
「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある
すららは、文部科学省が示す「ICTを活用した学習活動」のガイドラインに沿った教材であり、実際に多くの学校で出席扱いとして認められた実績があります。
しかし、学校側がすららの詳細を知らない場合もあるため、「すららが文科省の方針に適合した教材であること」を丁寧に説明する必要があります。
すららの公式サイトや資料を活用しながら、どのように学習を進められるのか、どのような形で学習の進捗を報告できるのかを具体的に伝えると、学校側も理解しやすくなります。
必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する
担任の先生がすぐに出席扱いの判断をできるわけではなく、最終的な決定権は校長先生にあります。
そのため、早い段階で教頭先生や校長先生にも相談し、学校全体としての理解を得ることが大切です。
また、すららの公式資料や、文部科学省のガイドラインに関する情報を一緒に持参すると、より説得力のある説明ができます。
学校側が「どうやって判断すればよいのか分からない」と感じた場合でも、具体的な資料を提示することで、スムーズに話を進めることができます。
注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある
出席扱いの申請において、不登校の理由が「体調不良」や「精神的な問題」によるものだった場合、学校側から医師の診断書や意見書を求められることがあります。
特に、長期的な不登校のケースでは、「子供が学習を継続できる状態であるかどうか」を確認するために、医師の意見が必要とされることがあります。
診断書の内容次第で出席扱いの申請がスムーズに進むこともあるため、事前に医師に相談し、適切な内容を記載してもらうことが大切です。
不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い
学校側は、不登校の原因をもとに、出席扱いの判断を行うことが多いため、「なぜ学校に通えないのか」を客観的に示すための診断書が求められることがあります。
例えば、心身の不調によって登校が難しい場合や、発達障害などの特性によって集団生活が困難な場合には、医師の診断書があると、学校側も出席扱いとして認めやすくなります。
特に、精神的な理由での不登校の場合、心療内科や精神科の診断書があることで、「家庭学習の必要性」がより明確になり、学校側の理解を得やすくなります。
通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える
診断書を作成してもらうためには、まず通院している医療機関(小児科・心療内科・精神科など)に相談する必要があります。
病院によっては、「どのような目的の診断書が必要か」を明確に伝えなければならない場合があるため、「出席扱いのための診断書をお願いしたい」と具体的に伝えることが重要です。
また、診断書の作成には時間がかかることもあるため、学校への申請期限を考慮し、早めに依頼するのが良いでしょう。
医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする
診断書を作成してもらう際には、単に「不登校である」という事実だけでなく、「学習を継続する意欲があること」や「家庭学習の環境が整っていること」を伝えることが重要です。
医師が診断書に「学習の継続が望ましい」「オンライン学習を活用することで、学習の遅れを防ぐことができる」などの前向きな内容を記載してくれると、学校側も出席扱いとして認めやすくなります。
そのため、すららを活用してどのように学習を進めているのか、どのようなサポートを受けているのかを具体的に医師に説明することで、より適切な診断書を作成してもらいやすくなります。
注意点3・学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること
すららを活用して出席扱いを認めてもらうためには、「単なる自習」ではなく、学校の授業と同等の学習内容を行っていることが求められます。
文部科学省のガイドラインでも、「ICTを活用した学習活動が、学校の教育課程に準じたものであること」が重要な条件の一つとされています。
そのため、学習時間や学習内容を計画的に進めることが大切です。
また、学校の指導要領に沿った形で学習を進めることで、よりスムーズに出席扱いとして認められやすくなります。
出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある
学校が出席扱いを認めるためには、「家庭学習が授業に準ずる内容であること」が重要視されます。
たとえば、教科書を読んだり問題集を解いたりするだけでは、学校の授業と同じ学習環境とはみなされにくいことがあります。
その点、すららは学校の学習指導要領に沿ったカリキュラムで設計されており、アニメーションを活用した授業や確認テストも含まれているため、学校側も納得しやすい教材です。
申請時には、「すららでどのような学習を進めているのか」を具体的に説明すると、より認められやすくなります。
学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する
学習時間についても、学校の授業時間と大きくかけ離れないようにすることが大切です。
文部科学省のガイドラインでは具体的な時間は定められていませんが、多くの学校では「1日2〜3時間程度」の学習が必要と考えられています。
すららを活用する場合も、無理のない範囲で学校の時間割に近い形で学習を進めると良いでしょう。
たとえば、午前中に2時間、午後に1時間など、生活リズムを整えながら計画的に進めることで、学校側からの評価も得やすくなります。
全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)
出席扱いの申請では、国語・数学・英語といった主要教科だけでなく、社会や理科、場合によっては体育や音楽などの副教科についても、バランスよく学習を進めることが求められることがあります。
特に、学校の教育課程に準じているかどうかを判断する際に、特定の科目だけを学習していると「授業と同等」とみなされない可能性があるため、すららを使って幅広い教科を学習することが大切です。
学校側と相談しながら、どの科目をどの程度進めるべきかを決めると、より確実に出席扱いとして認められやすくなります。
注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要
すららを活用して出席扱いを申請する場合、学校との連携が不可欠です。
学校側は、家庭学習の進捗を確認できる状況でなければ、出席扱いを認める判断が難しくなります。
そのため、定期的に学習状況を報告し、学校側と良好な関係を保つことが重要です。
特に、月に1回程度の学習レポート提出や、担任の先生との進捗共有を行うことで、学校側も安心して出席扱いを認めることができます。
出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い
多くの学校では、出席扱いを認めるために「家庭での学習状況を学校に報告すること」を条件としています。
そのため、学習の進捗や学習計画を定期的に学校と共有し、学校側が安心して出席扱いを判断できる環境を整えることが大切です。
学校側に「すららでどのように学習を進めているか」を伝え、学習状況が可視化されていることを理解してもらうことが重要になります。
月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い
すららでは、学習進捗を記録し、レポートとしてダウンロードできる機能があります。
この学習レポートを活用して、月に1回程度学校に提出すると、学習の継続性を証明することができます。
学校側が学習状況を確認できるようにすることで、出席扱いの判断がスムーズになりやすくなります。
学校によっては、提出頻度や報告方法が異なるため、事前に相談しておくと安心です。
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する
学校によっては、出席扱いの申請にあたり、家庭訪問や面談を求めることがあります。
これは、学習環境の確認や、子供の学習意欲を確認するためのものです。
事前に学校と相談し、どのような形で報告を進めるのが良いかを決めておくことで、スムーズに対応できます。
担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い
出席扱いの認定を受けるためには、担任の先生との連携も重要です。
定期的にメールや電話で進捗状況を報告し、「しっかり学習している」という事実を学校側に伝えることで、出席扱いの承認を得やすくなります。
学校側が状況を把握しやすいように、学習の進捗や困っていることなどもこまめに共有すると良いでしょう。
注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある
自治体によっては、出席扱いの認定にあたり、学校だけでなく教育委員会の承認が必要になる場合があります。
そのため、申請を進める際には、学校と相談しながら、教育委員会の方針や必要な書類を確認しておくことが重要です。
教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める
教育委員会に申請が必要な場合、学校側と連携しながら資料を準備することが求められます。
自治体によって、求められる書類が異なることがあるため、事前に確認し、適切な対応を進めることが大切です。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します
すららを活用して出席扱いを認めてもらうには、学校との円滑なやり取りや、学習の継続性を証明することが重要です。
出席扱いは文部科学省のガイドラインに沿った制度ですが、最終的な判断は各学校や教育委員会に委ねられています。
そのため、申請を成功させるには、学校側が安心して承認できるような工夫が必要です。
ここでは、すららを活用した出席扱い申請をスムーズに進めるための成功ポイントを詳しく紹介します。
ポイント1・学校に「前例」をアピールする
学校にとって、「オンライン学習を出席扱いにする」という判断は、前例がなければ慎重になりがちです。
しかし、すららはすでに多くの自治体や学校で出席扱いとして認められた実績があります。
そのため、事例を学校に提示し、すでに他の学校で実際に出席扱いが認められていることを伝えることで、学校側の理解を得やすくなります。
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的
すららは、全国の教育委員会や学校で不登校支援教材として活用されており、すでに出席扱いとして認められた実績があります。
そのため、学校側が「前例がないから不安」と考えている場合は、すららの出席扱い事例を紹介するとよいでしょう。
学校側が「他の学校でも認められているなら安心」と思えるように、実際の事例を提示することが効果的です。
すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する
すららの公式サイトには、出席扱いが認められた学校の事例が掲載されています。
そのため、学校との面談の際に、そのページをプリントアウトして持参すると説得力が増します。
具体的な事例を示すことで、学校側も制度の活用に対して前向きになりやすくなります。
ポイント2・「本人のやる気」をアピール
学校側が出席扱いを認めるかどうかの判断基準の一つに、「本人がしっかりと学習に取り組んでいるか」があります。
そのため、本人が意欲的に学習していることを伝えることが大切です。
学習の継続性や意欲を証明するための工夫をすることで、学校側の承認を得やすくなります。
本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い
すららでの学習を進める中で、本人が感じたことや、今後の目標を書いた文章を学校に提出すると、学習意欲の証明として役立ちます。
学校側は「家庭でどのように学習に取り組んでいるか」を確認したいと考えているため、本人の学習姿勢を示す資料があると、より納得しやすくなります。
面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い
学校によっては、出席扱いを判断する際に面談を行うことがあります。
その場合、本人が積極的に参加し、「自分なりに学習を続けている」「出席扱いを認めてもらいたい」と伝えることで、学校側の印象が良くなります。
本人の意欲を示すことで、学校側も安心して出席扱いを認めやすくなります。
ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる
出席扱いとして認めてもらうためには、「継続的に学習していること」が前提となります。
そのため、無理なく続けられる学習計画を立てることが重要です。
計画が非現実的なものだと、途中で挫折してしまう可能性があるため、本人に合ったペースで進められるよう工夫することが大切です。
継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる
学習計画は、本人のペースに合わせたものを作成することが大切です。
無理に長時間の学習を設定すると、継続が難しくなってしまいます。
1日2〜3時間程度の学習を目安にしながら、適度な休憩を取り入れることで、無理なく続けることができます。
すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう
すららには「すららコーチ」と呼ばれる学習サポートの専門スタッフがいます。
すららコーチに相談すれば、本人の特性や学習ペースに合わせた学習計画を提案してもらうことができます。
学校側に提出する学習計画も、すららコーチと一緒に作成することで、より説得力のある内容にすることが可能です。
ポイント4・「すららコーチ」をフル活用する
すららを活用する大きなメリットの一つが、「すららコーチ」が学習の進捗をサポートしてくれることです。
出席扱いを認めてもらうためには、学習の証拠を示すことが重要になりますが、すららコーチのサポートを受けることで、必要な書類を整えやすくなります。
出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる
すららコーチは、学習の進捗を確認し、学校に提出できるレポートの作成をサポートしてくれます。
学習証明書の作成にも協力してくれるため、保護者がすべてを管理しなくても、必要な書類をスムーズに準備することができます。
こうしたサポートを活用することで、学校側への説明もしやすくなり、出席扱いとして認めてもらう可能性が高まります。
すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します
良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました
良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない
良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました
良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった
良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました
悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました
悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった
悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった
悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。他のオンライン教材よりは高めの印象。
悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
すららが「うざい」という口コミがある背景には、いくつかの理由が考えられます。
まず第一に、個人の好みや感じ方は人それぞれ異なるため、一部のユーザーが感じる「うざさ」は、他のユーザーには当てはまらない場合があります。
また、すららの特性や機能について理解せずに利用している場合、操作性や情報の過多などが原因で不快に感じることもあるかもしれません。
さらに、ユーザー同士のコミュニケーションの在り方や、投稿されるコンテンツによっても「うざさ」を感じることがあるかもしれません。
ただし、すららは多くのユーザーにとって便利で有用なツールであり、適切に活用すればそのメリットを享受できることも事実です。
口コミは主観的な意見であるため、その中には様々な評価が含まれていますが、すららには様々な機能や使い方があり、それぞれの利用者が最適な方法で活用できる可能性を秘めていることも忘れてはいけません。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららは、発達障害を持つ子供や青少年の支援に特化した、専門的なカリキュラムを提供する教育機関です。
当機関では、発達障害コースにおける料金プランについて、ご興味をお持ちの方に詳細をご案内いたします。
料金プランには、一般的に以下のような構成がございます。
第一に、授業料金が含まれます。
発達障害に特化した教育プログラムを提供するため、専門の講師陣やカウンセラーが配置され、適切なサポートが行われます。
そのため、料金は一般のプログラムよりも多少高額になることがございます。
また、追加で必要となる教材や参考書、支援サービスの費用なども含まれます。
発達障害を持つ方々に最適な環境を整えるために、個々のニーズに合わせたカスタマイズが重視されます。
すららの料金プランに関する詳細は、お問い合わせいただいた際に、専門のスタッフが丁寧にご説明させていただきます。
発達障害コースへのご入学をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせいただき、ご自身やお子様に最適なサポートプランをご検討ください。
関連ページ: すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
不登校の子供達にとって出席管理は重要です。
すららのタブレット学習は不登校の子供でも学校の出席扱いになるかどうか疑問として挙がります。
実際に、教育委員会や学校によって異なるケースも考えられますが、一般的には出席として認められることがあります。
たとえば、すららのタブレット学習が学校のカリキュラムや教材に沿っており、学習時間や内容が適切である場合、学校側もその取り組みを受け入れるケースがあります。
しかし、それに関する具体的なガイドラインやポリシーは各地域や学校によって異なるため、事前に教育委員会や学校に確認することが望ましいでしょう。
不登校の子供にとっても、適切なサポートを受けながら、学習環境を整えることが重要です。
関連ページ: すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららのキャンペーンコードの使い方についてご案内いたします。
当社のキャンペーンコードを有効活用することで、さらにお得にお気に入りの商品を入手することが可能です。
まずは、お買い物カートに選んだ商品を追加してください。
その際、商品の決済画面に進む前に、キャンペーンコードを入力する欄がございます。
そちらに、ご利用いただきたいキャンペーンコードを正確に入力してください。
次に、「適用」ボタンをクリックしてください。
これにより、ご利用いただいたキャンペーンコードの割引が自動的に適用されます。
最後に、ご購入手続きを完了してください。
このようにすることで、すららのキャンペーンコードを効果的に活用し、お得な買い物をお楽しみいただけます。
ますます充実したショッピング体験をご提供できるよう、努めてまいりますので、どうぞご活用ください。
関連ページ: すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
すららは、オンライン学習プラットフォームとして多くの方々に利用されています。
しかし、退会をご希望される際には退会手続きが必要です。
すららを退会する方法について詳しく説明いたします。
まず最初に、すららにログインし、マイページにアクセスしてください。
マイページには、アカウント設定や会員情報の管理ができる項目がございます。
その中に「退会手続き」や「退会する」などの項目がございますので、そちらをクリックしてください。
退会手続きに進む際には、退会理由を選択する画面が表示されます。
理由を選択して次に進んでいきます。
その後、退会手続きが完了するまで、画面の指示に従って手続きを進めてください。
退会手続きが完了すると、すららのサービスは利用できなくなりますので、ご注意ください。
また、退会後も一部の情報は保存される場合がありますので、詳細については公式サポートにお問い合わせください。
以上が、すららを退会する方法についての手順となります。
退会に関するご不明点や疑問点がありましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
関連ページ: すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららをご検討いただき、ありがとうございます。
入会金と毎月の受講料以外に追加の料金がかかるかどうか疑問に感じられるかもしれませんが、安心してください。
すららでは、基本的なコース料金で全てのサービスがカバーされています。
つまり、入会金と受講料以外に、追加の料金は発生いたしません。
お客様が安心してコースを受講できるよう、透明性と信頼性を大切にしております。
何かご不明点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ますますのご活躍をお祈り申し上げます。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
1人の受講料を支払った場合、兄弟や姉妹などの家族と共有することは可能ですか?この疑問にお答えいたします。
通常、受講料は一人一人の受講者に対してのみ適用されるため、他の家族のメンバーが同じ料金でコースを受講することはできません。
ただし、一部の研修機関や教育機関では、家族割引やグループ割引などの特典を提供する場合があります。
具体的な受講規約や施設によって異なるため、最新の情報を公式サイトやカスタマーサービスにお問い合わせいただくことをお勧めします。
家族全員が教育を受けることが望ましい場合は、研修機関や教育機関に相談して、最適な料金プランを検討することをお勧めします。
すららの小学生コースには英語はありますか?
スララの小学生コースでは、英語コースも提供していますかどうか気になる方もいらっしゃるかもしれませんね。
お問い合わせいただきありがとうございます。
お応えいたしますと、はい、すららの小学生コースには英語コースがございます。
英語を学びたいお子さまのために、充実したコース内容をご用意しております。
英語を通じた国際感覚やコミュニケーション能力を伸ばしたい方に最適なプログラムです。
ぜひ、すららの小学生コースで英語を学ぶ楽しさを体験してみてください。
どんな疑問でもお気軽にお問い合わせくださいませ。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららを利用する際、専属コーチからはどのようなサポートが受けられるのでしょうか。
専門家が担当する個々のレッスンやトレーニングプランは、個人の目標やニーズに合わせて丁寧にカスタマイズされます。
コーチは生徒の進捗を追跡し、適切なフィードバックやアドバイスを提供することで、効果的な学習環境を提供します。
また、疑問や問題が生じた際には、すみやかに解決策を提供することも大切な役割のひとつです。
専属コーチは生徒一人ひとりの学習をサポートし、最良の成果を実現するために努めています。
すららのコーチは、生徒が目指す目標達成に向け、熱心かつ献身的なサポートを提供することをお約束いたします。
参照: よくある質問 (すらら公式サイト)
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ
今回の記事では、不登校の生徒がすららを利用して出席扱いになる方法について詳しく解説しました。
不登校の生徒や保護者の皆様にとって、出席扱いの制度や申請手順、注意点は非常に重要です。
まず、出席扱いの制度は学校や地域によって異なるため、正確な情報を把握することが必要です。
また、申請手順も煩雑な場合がありますので、事前に確認や準備を行うことが重要です。
不登校の生徒がすららを利用して出席扱いになる際には、注意点も押さえておくことが大切です。
例えば、正確な記録や証明書の提出が求められる場合もありますので、その点に注意して手続きを行う必要があります。
また、申請期限や条件についても確認し、適切に対応することが出席扱いの成功につながります。
不登校の生徒が出席扱いになるためには、制度や申請手順、注意点をしっかり把握し、適切に対応することが必要です。
すららを活用することで、不登校の生徒も学校生活に参加しやすくなるでしょう。
不登校の生徒や保護者の皆様が正確な情報を得て、円滑な手続きを行えるように、この記事がお役に立てれば幸いです。

